にんじんのしくみを解説~葉・根・花・種のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。
野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。
人気な根菜であるにんじんも、レースのように繊細な白い花を咲かせるのをご存知でしょうか?
見慣れた野菜のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。
この記事では、そんなにんじんのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。
にんじんについて

にんじん(学名:Daucus carota L.var. sativus Hoffm)は、原産地のアフガニスタンから世界各地に広まり、現在ではさまざまな品種が栽培されているセリ科ニンジン属の野菜です。
にんじんは大きく分けて、ヨーロッパで改良された太く短い「西洋系にんじん」と、中国で改良された細長い「東洋系にんじん」の2つの系統に分類されます。
西洋系にんじんには、特有のにおいが少ない五寸にんじん・ミニキャロットなどの代表品種があり、現在日本で流通するにんじんのほとんどを占めています。
一方、東洋系にんじんは栽培が難しく、現在では京野菜の「金時にんじん」や沖縄の「島にんじん(琉球にんじん)」など、限られた地域でしか生産されていません。
また、日本各地で野生化している外来種の雑草「ノラニンジン(学名:Daucus carota subsp. sativus)」は、にんじんと近縁の植物です。
ただし、チョウセンニンジン(朝鮮人蔘)やコウライニンジン(高麗人蔘)といった生薬として使われる漢字表記の人蔘(人参)は、ウコギ科のオタネニンジン(御種人蔘:Panax ginseng)という全く別の植物であり、食用にんじん(carrot)とは異なります。

にんじんは皮膚や粘膜を保護する「β-カロテン」を豊富に含んでいるため、根菜類の中では唯一、6つの基礎食品群のうち「第3群(緑黄色野菜)」に分類される野菜です。
食材としての旬は、春(4〜7月)と秋冬(11〜12月)の2回あり、春にんじんはみずみずしく柔らかな歯ごたえが特徴で、秋冬にんじんはしっかりと実がしまっており加熱すると甘みがぐっと引き立ちます。
にんじんのからだについて

にんじんは、私たちの食卓でおなじみの野菜ですが、じつは「葉・根・花・種」それぞれに異なる個性や役割があります。
どんな特徴があるのかを知ることで、普段の食卓にある野菜たちが、もっと身近でおもしろい存在に感じられるようになるかもしれません。
このページでは、にんじんの 葉・根・花・種――それぞれの部分が、どのように形づくられ、どんなはたらきをしているのかを、わかりやすく紹介していきます。
葉のはたらき

にんじんの葉っぱは、羽状複葉(うじょうふくよう)という細かく裂けた葉で、ふんわりとした繊細な見た目とパセリやセロリに似た爽やかな香りが特徴です。
成長とともに葉は硬くなっていきますが、若いうちに収穫された葉・間引き菜はやわらかく、美味しく食べることができます。
スーパーでは葉が切り落とされて販売されることが多いものの、実はこの葉には驚くほど多くの栄養が含まれています。
にんじんの葉には、β-カロテンは根よりやや少ないものの、ビタミンCは22mg(根の約4倍)、鉄分は0.9mg(根の約5倍)と、栄養価の高い成分が豊富です。
「にんじん菜」「葉にんじん」として、おひたし・和え物・スープ・ふりかけ・ジェノベーゼソースなど、幅広いレシピに活用され、料理サイトでも多数紹介されています。
ただし、葉は傷みやすいため、購入後は根と葉を切り分け、新聞紙に包んで野菜室へ入れ、できるだけ早めに使い切りましょう。

キアゲハの幼虫は、セリ科の植物を選り好みして食べる特性(食草)があり、にんじんの他にもミツバ・パセリ・フェンネル・セロリなどのセリ科植物が食害に遭いやすいです。
そのため、家庭菜園でにんじんを無農薬で育てていると、いつの間にかちょっとした「蝶の観察スポット」になっていることも少なくありません。
見ていて楽しい反面、葉っぱが食べられてしまうのは少し困りものですね。
根のはたらき

私たちが日常的に食べている「にんじん」は、植物でいう主根(しゅこん)の部分にあたります。
鮮やかなオレンジ色とやさしい甘みのもとになっているのが、豊富なβ-カロテン(プロビタミンA)です。
この「カロテン(carotene)」という語は、にんじんの英語名「キャロット(carrot)」の語源にもなっているほどで、まさににんじんを代表する栄養素といえるでしょう。
β-カロテンは体内で必要に応じてビタミンAに変換され、視力や肌・粘膜の健康維持、抗酸化作用、免疫力の向上など、さまざまな健康効果が期待されています。

β-カロテンは脂溶性で、生ではビタミンCを分解・失活する「アスコルビナーゼ」という酵素が含まれているため、「にんじんしりしり」「きんぴら」「グラッセ」のような油を使った炒め物は、β-カロテンの吸収率を高めるのに最適です。
また、β-カロテンなどの栄養素は皮の近くに多く含まれるため、皮をむかずに調理するのが良いでしょう。
にんじんは出荷時に機械で洗浄され、外皮のかたい部分はほとんど取り除かれているので、そのまま使っても安心です。
花・種のはたらき

にんじんは二年生植物であり、ある程度生長した株が10℃以下の低温に一定期間さらされると、花芽が形成される「春化(しゅんか)」という現象が起こります。
その後、気温の上昇と日照時間の増加(長日)によって、花茎が一気に伸びる「抽苔(薹立ち:とうだち)」が始まり、食用として収穫する場合は避けたい現象の1つです。
抽苔が始まると、栄養が花の成長に使われるため、「根の肥大が止まる」「包丁が通らないぐらい根が硬くなる」といった品質が落ちる変化が見られます。
これをあえて引き起こすことで、来シーズンのために種を採る「自家採種(じかさいしゅ)」ができ、野菜の“本来の姿”に触れることができる貴重な体験です。

にんじんの花は、セリ科植物に特有の「複散形花序(ふくさんけいかじょ)」と呼ばれる構造をしています。
これは、茎の先端から放射状に伸びた小軸の先に、さらに多数の小さな白い5弁花(小花)が集まって咲く、繊細でレースのような花形です。
にんじんの花には、「幼い夢」「慈愛」「あなたは魅力に満ちている」といった優しい花言葉もつけられています。

花が咲き終わると、花序全体は内側に丸くすぼまるように閉じていき、やがて果実を形成します。
この果実は細長い楕円形で、表面には鋭く長い棘(鉤状毛)があり、衣類や動物の毛にくっついて拡散される仕組みになっています。


にんじんの種子からは「キャロットシードオイル」と呼ばれる精油が抽出されます。
根の部分とは異なり、ややスパイシーさのある独特の香りが特徴で、アロマオイル・日焼け止め・スキンケア用品として利用されます。
まとめ

にんじんのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。
にんじんの葉・根・花・種、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。
そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。
「こびとの農園」では、そんなにんじんの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。
身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)
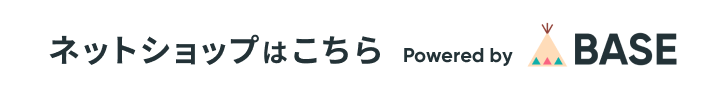

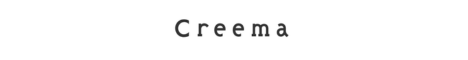
コメント
コメント一覧 (2件)
Everyone loves what you guys are up too. This type of clever work and exposure!
Keep up the excellent works guys I’ve you guys to blogroll.
Thank you so much! We really appreciate your kind words and support. We’ll keep doing our best! 🙂