ピーマン・パプリカのしくみを解説~葉っぱ・花・実のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。
野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。
緑色のイメージが強いピーマンですが、可憐な白い花を咲かせるのをご存知でしょうか?
見慣れた果物のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。
この記事では、そんなピーマンのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。
ピーマン・パプリカについて ~ピーマン・トウガラシ・パプリカは同種~

ピーマン(学名:Capsicum annuum L. ‘grossum’)は、ナス科トウガラシ属に分類される野菜で、原産地は中央アメリカから南アメリカ(中南米)とされ、コロンブスが1493年にスペインに持ち帰ったのが起源です。
英語名は “Bell pepper” “Sweet pepper”と表記されることが多く、ピーマンの語源はトウガラシを指すフランス語の “piment”かポルトガル語の “pimento”とされています
トウガラシの変種・栽培品種であることから分類学的にはトウガラシと同種で、しし群とベル群という2つの品種群がピーマンに区分けされています。また、ベル群のうち肉厚の大果種(100g以上)で、未熟果実で収穫されるピーマンとは異なり完熟果実で収穫される、黄・橙・赤などのカラーピーマンが「パプリカ」です。
一般に流通しているピーマンの品種として、京ゆたか・ニューエースなどがあり、苦みの原因であるクエルシトリン(ビタミンP)を抑制した「こどもピーマン」というものもタキイ種苗から出てきました。
参考記事:タキイ種苗株式会社HP「タキイ種苗×お茶の水女子大学共同研究成果「ピーマンの苦手成分」を解明」
ピーマン・パプリカの葉っぱについて ~食べられるの知ってますか?~

ピーマン・パプリカの葉は、やや尖った楕円形〜卵形で、葉縁は全縁(ギザギザがない)ながら、わずかに波打つのが特徴です。
表面はなめらかでツヤがあり、濃い緑色をしています。薄く柔らかい質感で、触れるとしっとりとした印象を与えます。ナス科特有のアルカロイド成分は含まれていますが、その量はごく微量であり、人間にとって強い毒性はありません。
あまり知られていませんが、葉かき(摘葉)や芽かきで取り除いた若い葉や芽は、食用にすることもできます。加熱調理すると食べやすく、おひたし・佃煮・油炒めなど、農家の知恵として受け継がれています。
ピーマン・パプリカの花について ~下向きに咲く白い花~

ピーマンやパプリカの花は、5〜7枚の花弁を持つ白色の花で、下向きに咲く傾向があるのが特徴です。葉の付け根(葉腋)に一輪ずつ咲き、可憐ながらも控えめな印象を与えます。
花は両性花で、ひとつの花の中に雄しべと雌しべがあり、自家受粉が可能です。両性花なのでオスメスありませんが、お尻が3つに分かれているものをオス(種が少なく身が硬い)、4つに分かれているのをメス(種が多くて身が柔らかい)と表現することがあります。
開花から結実までの期間は通常2〜3週間程度で、途中で花が落ちてしまう場合は高温・低温、肥料不足などによる株の体力不足が原因として考えられます。栽培では、株の生育を優先し着果数や果実品質を安定させるため、一番花を摘み取るのが一般的です。
ピーマンの花言葉は「海の恵み」「海の利益」で、完熟すると緑色の実が赤くなる姿から赤い珊瑚を思わせることや、フランスで赤い唐辛子を「菜園の珊瑚」と呼んだことが由来の一つです。一方、パプリカの花言葉は「同情」「憐れみ・哀れみ」「君を忘れない」で、下向きに咲く姿から少し切ない意味が込められています。
ピーマン・パプリカの実について

果実は中空の液果で、外果皮・中果皮・内果皮の三層構造を持ち、内部には多数の種子が胎座に付着しています。
ピーマン・パプリカの栄養は果皮よりも、タネ・ワタ(胎座)部分に多く含まれます。タネにはカリウムが豊富で、ワタには血流促進作用を持つピラジンが多く含まれます。苦味は増しますが、栄養面から見るとタネやワタを取り除かずに食べることがおすすめです。
赤色・黄色などへの変色、ピーマンのお尻が黒くなる「尻腐れ病」などは問題ありませんが、黒ずんだり斑点が出たりして腐っている状態は食べるのを避けるべきです。
パプリカは、緑ピーマンと比べて完熟している分、食物繊維以外の栄養成分が全般的に高くなります。
- β-カロテン:黄200μg<緑400μg<赤1100μg
- ビタミンC:緑76mg<黄150mg<赤170mg
- ビタミンE:緑0.8mg<黄2.5mg<赤4.7mg
β-カロテン・ビタミンEは脂溶性のため、油を使った料理で効率よく吸収できます。また、パプリカは果皮が厚くしっかりしているため、ビタミンCが調理中に流出しにくいのも特徴です。さらに、繊維に沿って縦に切ることで細胞が壊れにくくなり、苦味や香りが抑えられ、加熱後もシャキシャキした食感を保つことができます。
これらの特性を生かしたおすすめ料理には、ナムル・きんぴら・塩昆布和え・ツナ炒め・肉味噌炒めなどがあり、美味しい食べ方としておすすめです。
最後に

ピーマン・パプリカのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。
ピーマン・パプリカの葉・花・実、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。
「こびとの農園」では、そんなピーマン・パプリカの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。
身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

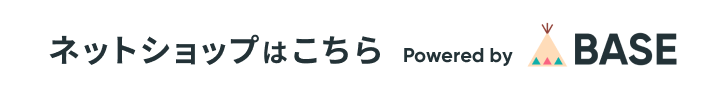

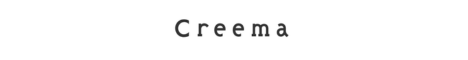
コメント