トマトのしくみを解説~葉っぱ・茎・花・実のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。
野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。
夏野菜の代表であるトマトは、星型の黄色く小さな花を咲かせるのをご存知でしょうか?
見慣れた野菜のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。この記事では、そんなトマトのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。
トマトについて ~ナス科って知ってましたか?~

トマト(学名:Solanum lycopersicum)は、中南米のアンデス高地を原産地とする、ナス科ナス属の野菜です。
トマトの語源は、メキシコ先住民の言葉であるナワトル語で”膨らむ果実”という意味の「トマトゥル(tomatl)」で、メキシコからトマトを持ち帰ったスペイン人がスペイン語「tomate」と称して広めます。
16世紀にヨーロッパに伝わり、日本には江戸時代後期に観賞用として導入されましたが、明治時代になってから本格的に食用として広まりました。赤茄子(アカナス)・唐柿(とうがき)・唐なすびなど、日本独自の呼び方もあります。
世界中で広く栽培されているトマトは1万種以上あると言われており、「丸玉系」「ファースト系」「ミニトマト系」など日本で品種登録されているものだけでも300種類以上を超えますが、大きさ(重さ)で3タイプに分類するのが一般的です(参照:農林水産省「トマトまるごとまるわかり」)。
- 大玉トマト:100g以上
- 中玉トマト(ミディトマト):30~100g
- ミニトマト:10~30g
トマトジュース・ケチャップでは、リコピンを多く含んだ商品が流行っており、生鮮トマトでも高リコピンを推しているものが増えています。
トマトの葉っぱについて ~トマチンとトライコームで防御力UP~

トマトの葉は、「奇数羽状複葉」と呼ばれる構造をしており、中央の葉柄から延びる軸に対し、3~5対の小葉が向かい合って並び、その先端の頂小葉が奇数になります。
小葉は卵形から楕円形で、葉の縁には細かいギザギザ(鋸歯)があり、葉の表面や裏面には細かな短毛がびっしりと密生しています。葉の表面と裏面には短く密生する毛(trichome)は、乾燥や強光から葉を守るだけでなく、植物ホルモン・防御物質の分泌源です(参考文献:Popowski, J., Warma, L., Abarca Cifuentes, A., Bleeker, P., & Jalaal, M. (2025). Glandular trichome rupture in tomato plants is an ultra-fast & sensitive defense mechanism against insects. Journal of Experimental Botany, eraf257.)。
トマトの葉は触れると青臭い独特な香りがしますが、これは葉に含まれる「トマチン(α-tomatine)」などのアルカロイド、「ヘキセナール」といった揮発性有機化合物などによるものです。これらの成分は昆虫や病原菌の忌避や殺虫作用など病害虫の侵入を防ぐ役割を果たします。
また、負傷時にはシステミン(systemin)などのシグナルペプチドが傷害対応を活性化し、さらにジャスモン酸経路を通じて全身抵抗性(SAR)を引き上げます 。
トマトの原産地である南米のアンデス高地という厳しい条件で進化してきたトマトは、自身を守り、生き延びるために高度な防御メカニズムを発達させました。
トマトの茎について ~実を大きくするなら芽かきは必須~

トマトの茎は単に植物体を支えるだけでなく、輸送・分岐・増殖など多様な役割を果たしており、植物全体の生命活動を支える中心的な器官です。
葉に含まれる「トマチン」などの成分・微細な毛(trichome)が茎にもあり、病原菌の忌避や殺虫作用をもたらします。
トマトの茎は成長とともに「節」を形成し、その節の付け根からは「葉」や「側枝(脇芽)」が出ます。脇芽をそのままにしておくと栄養が分散されるため、メインの茎以外の不要な脇芽を摘み取る「芽かき」を行い、果実の充実を図るのが一般的な栽培法です。
そこで未利用バイオマスであるトマトの脇芽の有効利用法として、消毒剤の開発が行われるなど面白い試みもあります(参考文献:伊藤雅子, & 森川豊. (2022). トマトの脇芽を利用した消毒剤の開発. あいち産業科学技術総合センター研究報告/あいち産業科学技術総合センター企画連携部企画室 編, (11), 46-49.)。
さらに、茎にぶつぶつとして「気根」が生じることがあり、厳しい環境下でも空気中の水分吸収などをするための構造です。病気の症状に感じてしまうかもしれませんが、特に問題なくトマトの実を食べることができます。乾燥気味に育てることで甘くなるトマトですが、この症状が出たら栽培環境の改善を検討するサインではあります。
トマトの花について ~黄色い星型の花~

トマトの花は黄色で、花弁が5枚に分かれた星型の小さな花を咲かせます。
トマトの花言葉は「感謝」「完成美」です。
花の中心には、雄しべと雌しべの両方が備わっている「両性花」という構造を持っています。雄しべは通常5本あり、それぞれの花粉が柱頭に自然に付着しやすくなるよう筒状に融合しているので、「自家受粉」が可能となり、外的な媒介が少なくても果実をつけることが可能です。
ただし、気温・湿度・風通しなどの環境条件が悪い場合には、人工的に花を揺らして花粉を柱頭に付ける「人工授粉」を行うこともあります。葉や茎ばかりが生長してしまう「つるぼけ」を防ぐために、最初に花がついた房(第一花房)は特に人工受粉などで着果促進させることが一般的です。
トマトの実について ~リコピンはすごい栄養・効能~

トマトの実は、花が受粉した後に膨らみはじめ、青い実をつけ、実は上から順番に熟して赤くなっていき、約1か月ほどかけて熟します。
トマトの実は、外果皮・中果皮・内果皮の三層構造のうち、中果皮と内果皮が多肉質・多汁質である果実「真正液果(漿果)」です。実の大部分は水分で構成され、栄養成分や機能性成分が豊富に含まれています。
果肉の内部は、ゼリー状の組織「胎座」に包まれており、そこに多数の種子が浮かんでいます。胎座は水分を多く含んでいるため、トマト全体のジューシーな食感に寄与しています。この部分が嫌いで取り除いてしまう方もいますが、リコピン・カリウム・ビタミンCの多くはこの部分に多く含まれていますので、取り除いてしまうと半分以上の栄養が損失してしまいます。
トマトの果実は、熟成過程で「クロロフィル(緑色素)」から「リコピン(赤色素)」へと色が変化し、その間に酸味が減少し甘味が増していきます。リコピンはカロテノイドの一種で、カロテンの2倍・ビタミンEの100倍の強い抗酸化作用を持ち、老化防止・生活習慣病予防・紫外線からの皮膚保護など、さまざまな健康効果が期待されています。にんにく・たまねぎ・油と一緒に加熱するとリコピンが体内に吸収されやすいことが、カゴメと名古屋大学の共同研究で発見されました(参考文献:カゴメ・名古屋大学 共同研究)。
ヨーロッパでは「トマトが赤くなると医者が青くなる」ということわざがあるほど、健康によい野菜なのです。美肌効果のあるビタミンC、老化を抑制するビタミンEが豊富で、ミネラルや食物繊維などをバランスよく含んでいます。リコピンの吸収は、絶食時間の長くなるほど血中リコピン濃度が大きくなることが示されているので、絶食時間が比較的長くなる朝ご飯におすすめです。(参考文献:青木雄大, 吉田和敬, 信田幸大, 砂堀諭, 西田由香, 加藤秀夫, & 菅沼大行. (2017). リコピン摂取時間帯がラットおよびヒトにおける体内吸収に与える影響. 日本栄養・食糧学会誌, 70(4), 147-155.)
【トマトの注目成分】
- βカロテン:540μg
- ビタミンC:15mg
- 葉酸:22μg
- カリウム:210mg
- 食物繊維:1mg
【トマト 可食部100gあたり成分 七訂日本食品標準成分表より】
最後に

トマトのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。
トマトの 葉・茎・花・実、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。
「こびとの農園」では、そんなトマトの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。
身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)


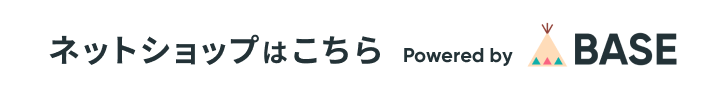

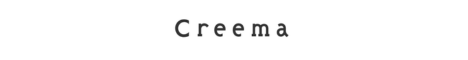
コメント